「ちゃんと寝ているはずなのに、朝からだるい」「布団に入ってもなかなか寝つけない…」
そんな悩みが続いているなら、見直すべきなのは“時間”よりも「睡眠の質」かもしれません。
本記事では、ぐっすり眠るための5つの考え方と、今日から試せる朝・昼・夜のルーティンを18個紹介します。
すべてを完璧にやる必要はありません。
気になったものを1つずつ取り入れて、「よく眠れて、よく動ける1日」を一緒につくっていきましょう。
ぐっすり眠るための5つの考え方
1. 体と脳をアクティブ→リラックスモードへ
もともと、人は夜になると体の中のホルモンバランスが変化し、アクティブモード(交感神経が活発)→リラックスモード(副交感神経が活発)へ切り替わるようにできてきます。
このホルモンバランスの自然な変化を邪魔しないのが大切。
さらに、意識的に日中に運動したり、夜には部屋を暗くしたりしてホルモンの自然な変化をうながせると⚪︎!
2. 光と体温が特に大事
このモード切替に影響が大きいのが「光」と「体温」。
人は光(特にブルーライト)を浴びると「今は昼間なんだ」と自動的に認識してアクティブモード側に変化します。
逆に暗くなると「夜になったな」と判断してリラックスモードになっていきます。
人類の長い歴史の中で「照明」というものが普及したのはつい最近のこと。
何万年もの間、「昼→明るい」「夜→暗い」が当たり前だったからそうなっているんでしょうね。
また、体温の変化も重要です。
人は体温が高いとアクティブに、低いとリラックスモードになります。
寝る前に体温が高い→低いと変化するようにすると、ぐっすり眠りやすいです。
3. 「眠らなきゃ!」と焦らない
眠りは本来「努力」ではなく「自然に訪れる現象」です。
「早く寝なきゃ」と思うほど脳が覚醒し、交感神経が働いて逆効果に。
ぐっすり寝れなくても、とりあえず「体と脳を休めれていればOK」と気軽に考えましょう。
4. 睡眠は休養!もし寝れなくても、体と脳を休められればOK!
眠るということは、体と脳、それに心を休めるためにするものです。
もしなかなか寝れなくても、休養自体は必要。
部屋を暗くして目を閉じ、体を横にしているだけでもかなり体や脳を休めることができます。
思ったように寝れなくてもしっかり休養はとって、翌日の昼間しっかり活動しましょう。
5. 休養をとる時間帯を決めておく
休養をとる時間帯をあらかじめ決めておくことも重要です。
例えば、22時〜翌朝6時までは休養時間だ、と決めておくのです。
この時間帯はもし寝れなかったとしても、スマホを見たりゲームしたりせず、体と脳を休めることに使いましょう。
そうすることで、休養をとるリズムができてきます。
睡眠の時間帯(就寝と起床の真ん中の時刻)が1時間以上ずれてしまうと、海外旅行の時の時差ボケと同様の状態になります。
これをソーシャルジェットラグと呼びます。
つまり、休みの日だけゆっくり寝る、というのは避けるべきなんですね。
睡眠の質向上のための朝・昼・夜のおすすめルーティン18選
たくさんのルーティンのアイデアをまとめました。
これだけあれば、何か一つくらいは「私もやってみようかな?」と思えるものがあるはずです。
もちろん、全てやる必要なまったく無し。
自分の生活に合わせて、うまく取り入れられそうなものを試してみてくださいね!
スッキリ起きるための朝のルーティン7選
夜にぐっすり眠るために大切なことは、
- 朝日を浴びる
- 体温を上げる
- 昼間の活動量を上げるために、カロリーを適切に摂取する
です。
1. カーテンを開ける
朝の光を浴びることで体内時計がリセットされ、眠気を促すメラトニンの分泌が止まり、脳と体が覚醒します。
自然光を取り入れるだけでも、心身のリズムが整いやすくなり、1日のスタートがスムーズになります。
2. 簡単にベッドメイクする
起きてすぐ簡単に布団と枕の位置を整えるだけで、脳が「活動モード」に切り替わります。
ちょっとしたことで達成感が得られ、部屋もスッキリするため、気分の切り替えと生活リズムの安定に効果的です。
3. 外に出て散歩する
朝の光と軽い運動は、セロトニンの分泌を促して自律神経を整えます。
5〜10分でも外に出ることで体温が上がり、日中の集中力や夜の睡眠の質も大きく向上。
4. 朝ごはんを食べる
朝食は体と脳のエネルギー補給。
血糖値を安定させ、午前中の集中力を維持します。
特に炭水化物とたんぱく質をバランス良くとることで、体内時計のリズムを整えよう。
5. 朝ごはんに暖かい汁物を加える
味噌汁やスープなど温かい汁物を取り入れると、内臓が温まり、代謝が活発に。
消化機能も整うため、1日のスタートがより快調になります。
6. 暖かい飲み物をのむ
白湯や温かいお茶を飲むことで、体温と血流が上がり、眠気をリセットできます。
冷たい飲み物ではなく、ぬるめの温度がポイント。
7. 軽い運動・体操・ストレッチをする
朝に軽く体を動かすことで、筋肉と血流が目覚め、脳も活性化!
無理のないストレッチや深呼吸を取り入れて、心身をリフレッシュさせましょう。
アクティブに過ごすための昼のルーティン3選
昼間は普通に活動していれば大丈夫だと思います。
体と脳の活動量を増やせるようにしましょう。
1. 昼ごはんを食べる
昼食はエネルギーの補給と午後のパフォーマンス維持に欠かせません。
食べすぎず、たんぱく質と野菜を中心に取ることで、午後の眠気を防ぎ、夜の寝つきも良くなります。
2. 適度な間食をとる
午後の低血糖を防ぎ、集中力をキープするために小さな間食が効果的。
ナッツやチーズ、果物など消化に優しいものを選びましょう。
食べすぎるとカロリーオーバーになるので気をつけて。
3. 20分以内の昼寝をする
昼食後の軽い眠気は自然な体のリズム。
20分以内の昼寝で脳をリセットし、午後の集中力と生産性を回復できます。
長すぎる昼寝は夜の睡眠に悪影響となるので注意しよう。
ぐっすり眠るための夜のルーティン8選
就寝に向けて体と脳をリラックスさせ、体温を下げていくのがポイント。
体温の下げ幅を大きくするためには、もとの体温を高くする必要があります。
就寝の1〜2時間前に少し体温を上げておくと良いでしょう。
また、就寝時は光・音・温度・湿度などを寝室環境を整えましょう。
1. 就寝2〜3時間前に軽い運動をする
軽い運動で体温を上げ、その後の自然な体温低下で眠気が生まれます。
激しい運動は避け、ストレッチやウォーキング、ラジオ体操などがおすすめ。
2. 夜ごはんは就寝3時間前に済ませる
寝る直前に食べると消化活動が続き、深い眠りを妨げます。
3時間前に済ませることで、体が休息モードに入りやすくなります。
3. 就寝1〜2時間前から照明は電球色・温白色にし、明るさを暗くしておく
光量を落とすことで、脳が「夜だ」と認識し、眠気ホルモンのメラトニンが分泌されやすくなります。
照明の色にいくつか種類がありますが、青系の色味の強いものは避けた方がいいです。
調光ができるのであれば、電球色や温白色がおすすめ。
4. 就寝1〜2時間前にお風呂(湯船)に15分つかる
ぬるめ(38〜40℃)の湯船に15分つかると体温が上がり、出た後に体温が下がるタイミングで自然な眠気が訪れます。
リラックス効果も抜群。
5. お風呂あがりに軽いヨガ・ストレッチをする
お風呂で温まった筋肉をゆるめることで、副交感神経が優位に。
心拍数が落ち、体と心が眠る準備に入ります。
6. 就寝1時間前からスマホ・TV・PCは見ない
ブルーライトはメラトニン分泌を妨げ、脳を覚醒させます。
デジタル機器を遠ざけ、照明を落とした静かな時間を過ごしましょう。
7. 寝る時は部屋をできるだけ暗くする(真っ暗にする)
光は体内時計に強く影響します。
豆電球や街灯の光も遮断し、完全な暗さにすることで深い眠りが得られます。
8. 途中で完全に目が覚めてしまった時は、ベッドから出てリラックス
眠れないまま布団にいると「ベッド=眠れない場所」と脳が学習してしまいます。
静かに部屋を出て、照明を落とした状態でリラックスすることが再入眠のコツ。
なお、あらかじめ寝れない時はどうするか決めておきましょう。
「寝れない…」となってから「どうしよう…」と考えていると、脳に負担がかかり余計寝れなくなってしまうからです。
【まとめ】睡眠の不安から解放されて、心も体もラクになろう!
睡眠の質を上げることは、「がんばって眠る」ことではなく、体と脳が自然と休める状態を整えることです。
「体と脳をアクティブからリラックスモードへ切り替える」「光と体温のリズムを整える」「『眠らなきゃ』と追い込まず、休養の時間をあらかじめ決めておく」。
そして「朝・昼・夜のルーティンから、できそうなものを1つずつ試してみる」こと。
いきなり完璧を目指さなくて大丈夫です。
「昨日より少しよく眠れた」が積み重なれば、きっと心も体もラクになっていきます。


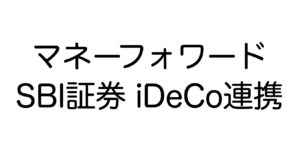
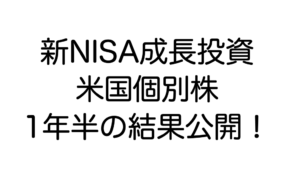
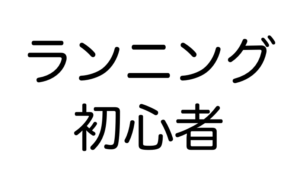
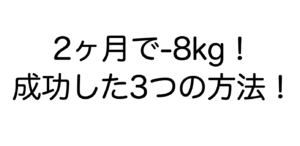
コメント